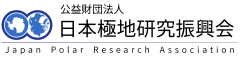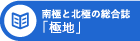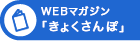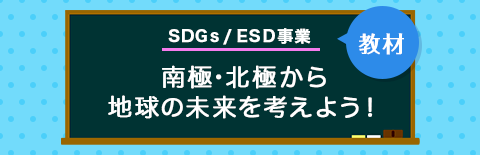理事長のごあいさつ
connection公益財団法人 日本極地研究振興会は「南極・北極(以下「極地」という)に関する研究、教育活動を助成し、あわせてその研究教育成果等の普及・啓発を行い、もって学術文化の向上発展に寄与すること」を目的として1964年に創設され、本年で60周年を迎えます。この間の皆様の温かいご支援・ご協力に深く感謝申し上げます。
中緯度に位置する日本から遠く離れた、南極や北極と呼ばれる「極地」の環境は過酷で極端ですが、氷山やオーロラなど人々を魅了する雄大で美しい自然の地でもあります。この南極や北極では、情報・システム研究機構 国立極地研究所が中心となり、全国の研究者や国内外の研究機関が共同・協力して未知の自然に挑む科学研究が実施されています。近年、この「極地」が地球上で大変ユニークで重要な場所であることがより強く認識されてきています。
現在地球温暖化をはじめとして地球環境に強い関心と危惧が持たれています。「極地」は人口密集地、工業や社会活動が活発な地域から遠く離れている上に、自身では汚染物質等を出さない場所なので、地球全体の気温や温室効果ガスの変動等の環境モニター観測に最適な場所となっています。南極における日本の科学観測は1957年の国際地球観測年を端緒に現在まで継続的に行われており、地球の気候の長期変動等を知る上で大変貴重なデータを提供しつづけています。
この環境変動を知るという面に加えて、近年「極地」は他の地域に比べ、より急速に温暖化が進んでいること、そして「極地」が地球全体の環境変動に重要な影響を与えるという「能動的」な役割が明らかになってきました。そのため、「極地」の観測やそれを基にした科学研究の促進・強化が、地球全体の環境の理解・解明、その変動の将来予測をする上で大変重要になっています。
さらに国境がないことも南極の重要な特色の一つです。それを可能としているのは科学的調査の自由と国際協力、領土主権の凍結等を謳っている南極条約(1961年発効)です。南極における科学研究活動は、南極研究科学委員会という国際組織の下で多くの国々が協力しあって行われています。一方、北極でも、日本が拠点を置く地域の一つであるノルウェー領のスヴァールバル諸島では、スヴァールバル条約(1925年発効)により、すべての条約加盟国は等しく経済活動、科学研究活動を行うことができます。世界の多くの国々や地域で紛争が起きている現在、解決には国境を超えて協力し理解しあうことが必須ですが、「極地」はこの理想を科学の世界で実現している好例と言えます。また汚染物質の管理・処理等も、強い規制の下で徹底して行われており、その方法や知見も広く一般社会で参考になるものです。
「極地」が持つこれらのユニークで優れた点、科学観測研究等の活動と成果の多くは、「持続可能な開発目標(SDGs)」に関係しています。日本極地研究振興会は「南極・北極から地球の未来を考える」というミッションステートメント実現のために、SDGsの普及啓発活動や「地球規模の諸課題を主体的に捉え、その解決に向け自分で考え、行動する力を身に付けるとともに、新たな価値観や行動等の変容をもたらす」(ESD)教育への支援等、今後も多様な取り組みを行ってまいります。
60年にわたり築かれてきた日本極地研究振興会を継承・発展させ、ドームふじにおける新たなアイスコア深層掘削計画の開始や北極域観測船の建造に見られるように益々発展する極域研究への支援はもとより、より良い社会の実現に向けて今まで以上の貢献ができるように努力してまいります。
皆様には引き続き日本極地研究振興会へのご支援・ご協力をお願い申し上げます。
略歴
1950年生まれ(73歳)
東京大学理学系大学院地球物理修士課程修了、理学博士(東京大学)。名古屋大学太陽地球環境研究所所長、名古屋大学理事・副総長、情報・システム研究機構長等を歴任。日本学術会議会員(2014-2020年)、ノルウェー科学文学アカデミー会員。地球電磁気・地球惑星圏学会田中館賞、Beynon Medal受賞。名古屋大学名誉教授、情報・システム研究機構名誉教授。専門は宇宙科学(地球磁気圏・電離圏物理学)。